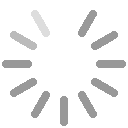iPS細胞から作製、インスリンを出す細胞を糖尿病患者に移植する臨床試験実施 京大病院が発表
京都大病院は14日、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが分泌されなくなる1型糖尿病の患者1人に対し、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製した「膵島細胞」というインスリンを出す細胞を移植する臨床試験(治験)を実施したと発表した。患者は経過良好で既に退院しており、最大5年間にわたり経過観察する。
1型糖尿病は、膵臓の細胞が自己免疫などによって壊れて発症する。血糖値を下げるため毎日インスリンを皮下に自己注射する必要があるほか、低血糖による失神が起こることもあり、実用化すれば患者の負担軽減につながる可能性がある。
今回の治験は、治療の安全性を確かめることが目的で、血糖値管理が特に難しいとされる「ブリットル型」の1型糖尿病患者が対象。2例目に向けて準備を進めており、計3例を予定している。治験責任医師の矢部大介京大教授は「2030年代の実用化を目指したい」とした。
病院によると、1例目の患者は40代女性。手術は2月に実施した。作製した膵島細胞を数センチ四方のシート状にし、下腹部の皮下に複数枚移植した。シートから出るインスリンが毛細血管などから吸収されることにより、血糖値の安定が期待されるという。
手術後の合併症などはなかった。現時点での効果については明らかにしなかったが、移植自体は「十分に成功した」とした。
次の段階の治験では有効性を確かめる。企業治験で、日本のほか米国や欧州など世界的に実施する計画だという。
京大と武田薬品工業が共同研究してきた技術を引き継ぎ、iPS細胞を使った再生医療に取り組む企業「オリヅルセラピューティクス」(神奈川県)がシートの製造に携わった。